2025/12/16-16:32

メンタルさんのぼやきのコミュです。。
ぼやきで、少しだけ、安定したら、
うれしいです。。
利用してください!
こちらはレスはありません。。
完全なひとりごとでお願いいたします。。
誹謗...
 続きを見る
続きを見る
2025/12/03-20:25

在宅ワークをやります。。
気楽にしていきたいですね。。
レスはありませんので、、ひとりごとで。。
誹謗中傷はお断りします。。
 続きを見る
続きを見る
2025/12/02-20:32

旧みんなでコロナを乗りきろうの会
思いもよらぬことが次々と起こるこの世の中。
このコミュニティでは、不安な中でも、こんな工夫をして楽しく過ごせたよとか、こんな環境だからこそ、こんなことができた...
 続きを見る
続きを見る
2025/02/22-02:45

「ここをこんな感じに直してほしい」
「こんな機能があったらすごく便利」
などなど、ご意見・ご要望があればお気軽にどうぞ
同意見が多数あるものについては、なるべく早く対応するつもりです。
サービス向...
 続きを見る
続きを見る
2024/09/28-16:38

【うきうき】家計簿の初心者です。
「でも、事務局に問い合わせする程ではないしぃぃぃ。。。
どうすりゃいいのぉぉぉぉ!?」
ってお困りの方、バシバシ質問しましょう。
で、知識と経...
 続きを見る
続きを見る
2024/08/15-21:28

みなさんの「おうちごはん」教えてください。
今日の晩ごはん。
節約料理。
簡単な1品。
おすすめのメニュー。
なんでもOKです♪
お互いの知恵を重ねて、楽しくおいしい毎日を(@´゚艸`)ウフウフ
 続きを見る
続きを見る
2024/07/19-20:28

食べ物の写真をアップして楽しめたらなぁ…って思ってコミュニティーを作ってみました。
 続きを見る
続きを見る
2023/10/26-12:37
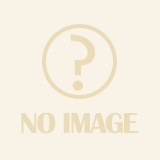
お揃いのカップルコーデをすると、彼女や彼氏との距離がさらに近くなると感じがします。
愛し合っているカップルの多くは、カップルお揃いのネックレスやブレスレット、指輪などを身に着けることを好みます。 同じ...
 続きを見る
続きを見る
2023/08/31-05:43

①2019年春~終活5カ年計画(仮称)策定
②2021年暮~「終活三年計画」正式策定~火災保険会社及び不動産業者の現認(隣りとの境界線?周辺環境の利便性を権利書及び登記簿、現況で確認)を得た。若干安...
 続きを見る
続きを見る
2019/03/23-11:41
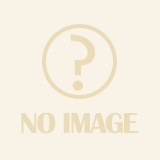
営業時間
平日14:00~19:00
長期学校休業日
8:00~17:30
土 8:00~17:30
日曜日休業日
HP↓
https://ukiuki.in/ukiuki/community/com...
 続きを見る
続きを見る